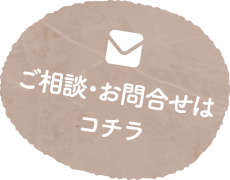昭和耐震住宅

今回紹介するのは新耐震基準を満たした、賃貸物件である。
「新耐震基準」は1981(昭和56)年6月1日に建築基準法の一部改正で施行された基準で、
“新耐震基準の考え方は、中規模の地震(震度5強程度)に対しては、ほとんど損傷を生じず、極めて稀にしか発生しない大規模の地震(震度6強から震度7程度)に対しては、人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害を生じないことを目標としたものである。”(引用:国土交通省 HP) とされている。
このお家は1970(昭和45)年築ではあるが、今回、リノベーションにて新耐震基準を満たしたお家となった。


しかも、この家には井戸があり、庭(耕せば畑)として使用できる場所も付いている。
リノベーション前は床下に眠っていた井戸。飲料水としての使用はできないが、庭や畑にまくには十分である。


家の中についてもご紹介。






↑ 畳だった部屋をフローリングに変えたお部屋。かつ、襖で仕切っていたお部屋を壁で仕切ったお部屋でもある。
昭和に建てられたお家の特徴として、部屋同士を襖や障子で仕切っていることが挙げられる。
可動式の襖や障子を使うことで、空間を柔軟に使うことができる。人が集まることが多かった昭和の時代においては、必要に応じて空間を広く使える仕様は便利だったのではないだろうか。
時代と共に人々の生活は少しずつ変わり、それに合わせて住まいの形も変化してきた。
リノベーション前は襖で仕切られていた空間も、リノベーション後は壁を設け、家具の配置がしやすい空間、プライバシーが保てる空間へと変えた。
もしかすると、更に30年後、40年後には、また違った間取りが合うかもしれない。
それでも、住まいは変えられる。たとえ古い家であっても、リノベーションを通して、その時代に合わせた形へ変える事ができる。古いものを活かしながら、現代の暮らしに寄り添う家へと整えていくことが可能である。
当社が不動産業者として、またリフォーム・リノベーション業者として目指すところは、建てては壊す、古くなったら新しいものに変えるという建築社会ではなく、古くとも使えるものは使う(修理・補修して使う)という、「循環型建築社会の市場創造(建物の循環を当たり前にすること)」である。また、それは何故かというと「未来のこども達」のためである。
例えば、ガラス障子の下桟と敷居部分。経年劣化と共に、下桟も敷居もすり減り、変形することで動きが悪くなる。ガラス障子はデザイン性が有り、現代では貴重なもので処分してしまうのはもったいない。
その為、職人の手によって削り、補修を行い滑りを良くしてもらう。古くとも修理・補修を行いこれからも使いつづける。細かな作業であり、決して目立つ仕事ではないかもしれないが、その作業(技)ができる職人に我々の活動は支えられている。
※ガラス障子だけでなく、型ガラスの窓も必要時は補修しながらも残していく。

補修したことに気づかない部分ではるが、動きが悪いと目立つ部分でもある。










.jpg)
最後までご覧いただきありがとうございました。
当物件は長崎の魅力を発信中のYoutuber 品川さんのチャンネル「長崎暮らし」でもご紹介させていただいております。
是非、ご視聴ください。